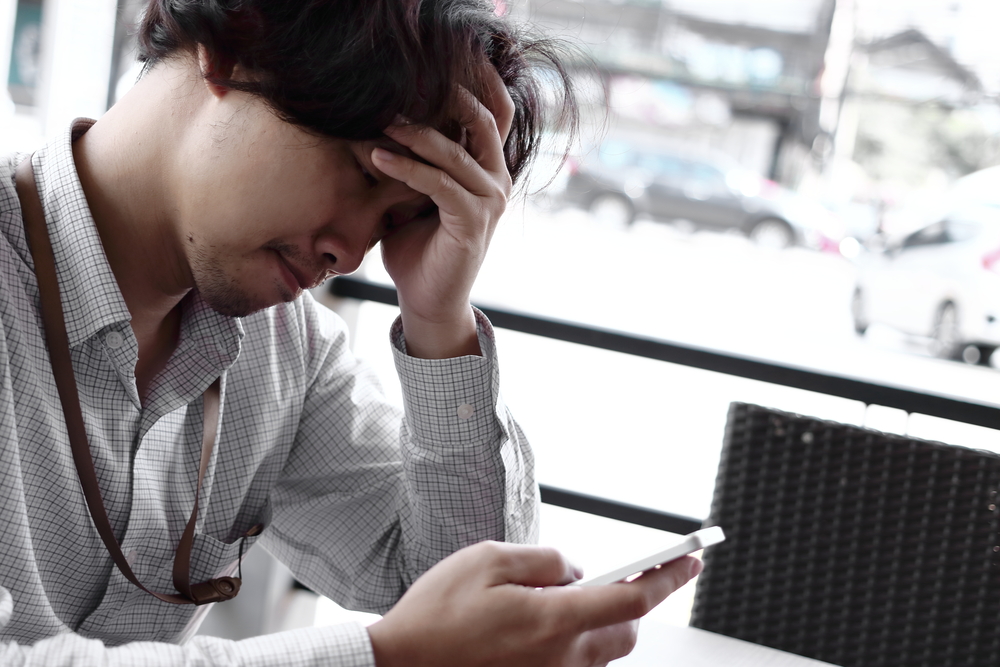「仕送りって、どのくらいの人がしているの?」
「仕送りっていくらくらいすべき?」
「毎月の仕送りが大変……」
そういった悩みを抱えていませんか?
親に仕送りをしたいと思ってはいても、自分の家計を考えると不安も多いですよね。
実際に仕送りをしている世帯は2%と言われています。
この記事では、世の中の仕送り事情や仕送りと贈与の違い、仕送りのメリット・デメリットを詳しく紹介します。
目次
1.世間の仕送り事情


1-1. 親への仕送りの平均額
2019年度の国民生活基礎調査によれば、親への仕送り額の平均は月額54,000円です。
平均額だけ見ると高いと感じる人も多いかもしれません。
ただし、これは一世帯あたりの平均のため、夫婦で合わせて10万円程度を仕送りしているなどの世帯のデータも含みます。
実際のところ、仕送りしている月額で最も多かったのは2~4万円です。
1-2. 仕送りをしている人はどのくらい?
2019年度の国民生活基礎調査では、仕送りをしている世帯数のデータもあります。
仕送りをしている世帯数は全世帯のうちの約2%で、約50世帯に1世帯であると言えます。
意外と多いと感じるかもしれません。
ただし、この統計には年代別や収入のデータがありません。
そのため、世帯年収が比較的少ない若い世帯などは、さらに少ない可能性もあります。
2.生活のための仕送りは贈与税の対象にはならない


2-1. 仕送りと贈与の違い
親子には、相互扶養義務があり、一般的に仕送りは贈与税の対象にはなりません。
ちなみに、仕送りは、扶養者が被扶養者へ生活のために必要な金銭を送ることを指します。
一方贈与は、財産を無償で提供する意思を示すことです。
ただし、多額の仕送りは課税されます。
仕送りが非課税になる上限は年間110万円です。
2-2. 年間110万円以上の仕送りは、申告が必要
年間110万円以上の仕送りは、それが生活のためであっても課税の対象です。
贈与税を納めるために確定申告を忘れず行いましょう。
3.親を扶養に入れる


3-1. 扶養家族(税制上)となる条件
親と別居していても、親の年間の総所得が38万円以下であり、子(納税者)と生計が同じであるという条件で、親を税制上の扶養に入れられます。
「生計が同じである」とは、国税庁によれば、①生活費や額資金、療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、就学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときが挙げられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm
3-2. 親を扶養に入れるメリット
親を扶養に入れられれば、課税の対象となる所得が減り、家計の負担が減ります。
具体的には、70歳未満で別居している親を扶養に入れれば、所得税の控除は38万円で、住民税は33万円控除されます。
70歳以上で別居している親を扶養に入れた場合は、所得税が48万円、住民税は38万円が控除されます。
また親が要介護に認定されている場合には、介護サービスを利用した場合に医療費控除の対象になるものもあります。
4.仕送りで自分を苦しめないための対策


4-1. 仕送りの前に、自分の家計を見直す
自分の家計も苦しいのに、親にお金を送っていませんか?
自分や同居家族の生活費を引いても無理のない仕送り金額の範囲を知ることは、無理せず仕送りを続けるために必要です。
特に義理の両親に仕送りをしているとなると、家計が苦しいことをパートナーに伝えにくいですよね。
パートナーに家計を知ってもらうためにも、家計簿などに家計をまとめておくと良いでしょう。
4-2. 専門家に相談
家計を見直したり、資産形成をしたりする専門家として、ファイナンシャルプランナーがいます。
ファイナンシャルプランナーは、FPとも表記されます。
自分では家計をまとめるのが難しいと感じたり、仕送りへの不安を抱えたりしている場合にはファイナンシャルプランナーに相談してみましょう。
4-3. 仕送りは義務ではない
仕送りを続けていると、仕送りありきで家計を考えてしまいがちです。
しかし、仕送りは義務ではありません。
家計が苦しいと感じるときは、無理せず親と話し合うことも考えてみましょう。
5.まとめ
まとめると、仕送りの平均額は月額54,000円です。
親を扶養に入れることで、控除が受けられるメリットがあります。
仕送りをするのが大変だと感じたら、まずは家計を見直しましょう。
専門家に相談することもおすすめです。
それでも、仕送りで家計が苦しいと感じたら、親と話し合ってみると良いです。