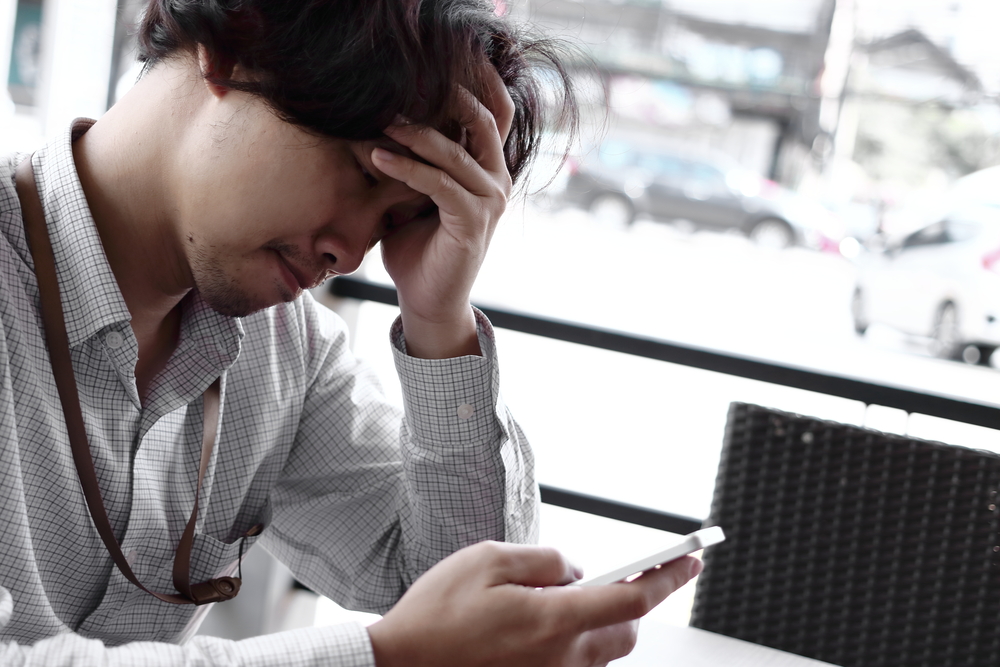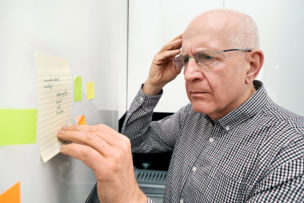
「最近、親がいろんなことを忘れちゃうけど、どう対応したらいいのかわからない」
このような悩みを抱えていませんか?
もしかしたら、それは認知症による記憶障害かもしれません。
厚生労働省の「認知症施策の総合的な推進について」によると、認知症は年齢と共に増え、80歳以上の有病率は20%を超えています。
つまり、85歳以上の方の約四分の一は認知症を発症しているのです。
この記事では、認知症の中核症状である記憶障害について、症状や種類、対応を解説します。
目次
1.記憶障害とは、認知症の中核症状の一つ
記憶障害は、認知症の中核症状の一つです。
中核症状とは、認知症の重要な部分にあるとされる症状のことです。
脳が病気により変化することで、認知機能が低下し引き起こされます。
1-1.記憶障害ともの忘れ、体験全部忘れるのが記憶障害
もの忘れと記憶障害との違いは、症状と自覚があるかどうかです。
もの忘れは、年を重ねると誰にでも起こりえるもので、「いつ」「どこで」「誰と」といった体験の一部分を忘れます。
そして、もの忘れをした場合は自覚があります。
一方で、記憶障害は、体験の全体を忘れてしまい、自覚がなく日常生活に支障をきたす症状です。
例えば、「昨日何を食べたことを忘れている」「病院の予約を入れたことを忘れてしまう」など、全体を忘れてしまいます。
1-2.記憶障害の症状
記憶障害の症状は、薬を飲み忘れたり、二重に飲んでしまう、ついさっき言われたことを忘れてしまう、今何しているかわからなくなる、質問を繰り返すなどです。
体験全体を忘れることから、話しのつじつまが合わなかったり、作り話をしてしまうこともあります。
また、ものを誰かに盗られたと思い込む、抗うつ状態を引き起こすことも少なくありません。
1-3.記憶障害の進行
記憶障害の進行の仕方は、認知症の種類により異なります。
・アルツハイマー型認知症:記憶障害が初期から現れ、ゆっくり進行する。
・脳血管性認知症:初期は症状を自覚できるが、良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、進行する。
・前頭側頭型認知症:初期は記憶障害が目立たない。
2.5種類の記憶障害
記憶障害には、5つの種類があります。
それぞれ説明していきます。
2-1.短期記憶障害
短期記憶障害とは、今日が何月何日なのかわからない、どこに物を置いたか忘れてしまい、いつも探し物をする、同じ質問を繰り返すなどの症状がみられる記憶障害です。
認知症の方は新しい記憶から失われ、次第に思い出せないことが増えていきます。
2-2.長期記憶障害
長期記憶障害とは、「自分の職業」「家族の消息」「通った学校の名前」など、普段は考えなくとも会話や古い写真がきっかけで思い出せる昔の記憶が、抜け落ちてしまう記憶障害です。
症状が進行すると、家族の顔や名前、自分が結婚したことなども忘れていきます。
2-3.エピソード記憶障害
エピソード記憶障害とは、自分が生活したことや体験したこと、そのものを忘れてしまう記憶障害です。
家族や周囲の人から「あの学校に通ったね」「ここに行ったね」と話されても、体験自体を忘れてしまっているため、話がかみ合わなくなります。
2-4.意味記憶障害
意味記憶障害とは、ものや言葉の意味を忘れる記憶障害です。
単語や人名が出てこなくなり、会話で「あれ」や「それ」などの表現が多くなります。
語彙力が低下するため、意思疎通が難しいです。
2-5.手続き記憶障害
手続き記憶障害とは、繰り返し学習や練習により身についた技術など、「身体が自然に覚えている」ことができなくなる記憶障害です。
例えば、洗濯や料理、自転車に乗るなど、今まで当たり前にできたことができなくなります。
3.症状が現れたら


認知症の記憶障害が現れた場合の対応について説明します。
3-1.認知症の検査を受けに行く
まず、初期症状が現れたら、病院の物忘れ外来に行き検査をしましょう。
初期症状の確認は以下が目安です。
・同じことを何回も話す
・よく探し物をする
・料理や買い物に手こずる
・お金の管理ができない
進行性の障害なため、完治はできませんが、進行を遅らせる薬があります。
主治医に状態を説明し、本人に合った処方をしてもらいましょう。
3-2.家族の接し方
記憶障害の対応によって、進行が促進してしまうことがあるので、家族の接し方は重要です。
ここでは、家族の対応の仕方について説明します。
3-2-1.受けとめる
記憶障害を抱える方は、自身に起きていることが理解できず、混乱や不安を抱えています。
そのため、周りが抜け落ちている記憶に対して否定したり訂正すると、ウソをつかれたと感じてしまい、さらに不安に陥ります。
事実とは違うことを言われても、受けとめることで安心してもらいましょう。
3-2-2.環境を整える
記憶障害により、食材管理ができない、水道を出しっぱなしにしてしまう、支払いを忘れるといった日常に支障をきたすことがあります。
その場合は、宅食サービスの利用やガスと水道は周りに人がいるときだけ使えるようにする、支払いを口座引き落としにするなど、環境を整えましょう。
3-2-3.繰り返して覚える
新しいことを覚えてもらう必要がある場合は、ひとつひとつ繰り返しましょう。
また、使用順番を番号をつける、絵を使うなどして、覚えやすいよう工夫が必要です。
3-2-4.症状だと理解する
記憶障害の症状として、質問を繰り返したり、約束を破ってしまったり、すぐ忘れてしまうことがあります。
振り回されそうになっても、認知症の症状であることを理解しましょう。
怒りそうになった場合は、その場を離れて冷静になる時間を持つのが大事です。
4.記憶障害の予防と改善
記憶障害を予防や改善するには、認知症の予防や、レクリエーションが効果的です。


4-1.認知症の予防
アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症は、生活習慣病との関連が強いです。
そのため、バランスの良い食事の摂取や、適度な運動を行い予防しましょう。
>>認知症の予防についての記事はこちら
https://carers-navi.com/prevention
4-2.回想法
回想法は、昔を思い出してもらう予防法です。
幼少期の写真や出来事を題材に、思い出話をしてもらいます。
昔を思い出すことで、記憶障害の予防になるだけでなく、症状が現れた場合不安の軽減や、うつ感の改善にも繋がります。
4-3.血流改善
記憶の機能低下を防ぐには、神経細胞に酸素や栄養素が十分に届けられるのが重要です。
脳内の血流を良くするために、首や肩のストレッチを行いましょう。
また、長時間の昼寝をしない、就寝3時間前には夕食を済ませるなどして、睡眠の質を良くするのも大切です。
5.まとめ
いかがだったでしょうか。
記憶障害は、もの忘れとは異なり体験したこと全体を忘れてしまい、進行していく障害のことでした。
大切なことは、記憶障害の症状により本人も混乱して不安を抱えているため、周囲の人は理解し受け止めることです。
今回ご紹介した対応の仕方を参考にしていただければ幸いです。