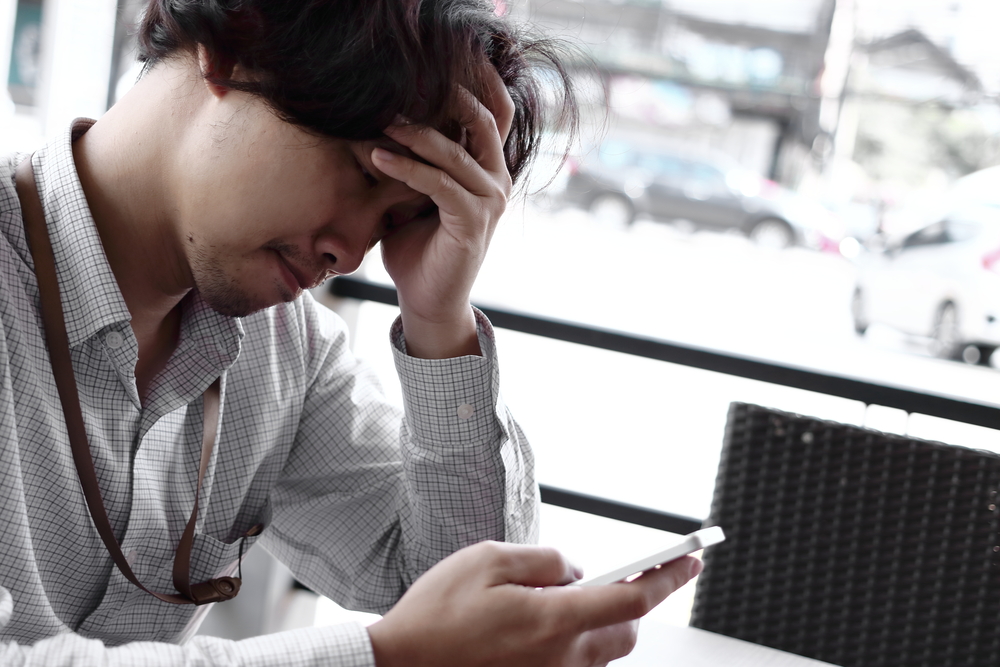最近、物忘れがひどい。。。
お父さんが、ずっとスマホを触っていて心配。。。
スマホ認知症ってどのくらい危険なの?
このような悩みや疑問を抱えているのではないでしょうか?
近年では、若者だけでなく、高齢者が使う機会が増えたスマートフォン。
しかし、スマホやPCなどのデジタル機器の使い過ぎにより、記憶力や集中力の低下や記憶障害など認知症と似た症状が現れる場合があります。
これをスマホ認知症と言います。
この記事では、スマホ認知症の概要や原因、4つの対策を解説します。
目次
1.スマホ認知症とは


スマホ認知症とは、スマホやPCなどのデジタル機器の使い過ぎにより、記憶力や集中力の低下や記憶障害など認知症と似た症状が現れることを言います。
また、スマホ認知症は、デジタル認知症と呼ばれることもあります。
主な症状は、「病的な物忘れ」です。
認知症と呼ばれますが、病気としての認知症には分類されません。
このスマホ認知症は現代において、深刻な社会問題になりつつあります。
スマホ認知症は、高齢者に限らず、子どもを含めたすべての年代で発症する可能性があります。
2.スマホ認知症の仕組み


なぜスマホを使いすぎると認知症の症状が出てしまうのでしょうか?
2-1.長時間の使用による脳疲労
スマホの長時間使用は、脳を疲労させてしまいます。
動画やニュースを何気なく見ている間にも、脳は働き続け大量の情報をインプットしています。
脳の疲弊で、記憶力や思い出す機能が弱まってしまうのです。
その結果、記憶障害など認知症のような症状が現れてしまいます。
取り込んだ情報を思い出す機能が弱まってしまいます。その結果、スマホ認知症のような病的な物忘れが生じてしまうこととなるのです。
2-2.情報過多でインプット機能が低下
脳は、情報を取り込み、思考や行動といったアウトプットを繰り返すことで成り立っています。
しかし、スマホで大量にインプットした情報をアプトプットすることは難しいです。
その結果、アウトプットする力が低下し、人の名前や漢字が思い出せなくなったりしてしまいます。
2-2.ブルーライトによる睡眠障害
スマホやPCはブルーライトを発します。
ブルーライトは、目や脳に悪影響を及ぼします。
特に、就寝前にブルーライトを浴びると、メラトニンという睡眠に作用するホルモンが減少します。
その結果、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めてしまったりと、睡眠障害の原因となってしまいます。
脳は、就寝中にインプットした情報を処理しているため、睡眠障害は物忘れなどを促進してしまいます。
3.アルツハイマーと「スマホ認知症」との違い


アルツハイマー型認知症とは、最も一般的な認知症の一種です。
以前までは、アルツハイマー型認知症=認知症とされていました。
また、認知症の半数近くをアルツハイマー型認知症が占めていると言われています。
アルツハイマーとスマホ認知症の違いは、脳の萎縮の有無です。
アルツハイマーは、脳が萎縮して発症すると考えられていますが、スマホ認知症には脳の萎縮は見られません。
また、認知症は完治することがほとんどないですが、スマホ認知症は完治できます。
4.スマホ認知症の対策


4-1.休息時間を設ける
スマホ認知症の予防のためには、脳に疲労をためないことが大切です。
そのため、意識的にデジタル機器に触れない時間を作り、脳と目を休めましょう。
日々の生活の中に休息時間を組み込むことをおすすめします。
4-2.一日の使用時間などルールを決める
一日の中で3時間以上は使わないなどルールを決めましょう。
他にも、就寝2時間前は触らない、電車に乗っている時間は使わないなどでもよいでしょう。
自分の中で、可能な範囲でマイルールを作ってみてください。
4-3.すぐに検索しない
思い出せないときに、すぐ検索することは避けましょう。
がんばって思い出したり、周りの人に尋ねて見ることでスマホ認知症を予防できます。
特に高齢者の場合は、使わないと脳の機能はどんどん低下してしまいます。
すぐに検索をせず、別の方法を考えて見ましょう。
4-4.なるべく通知を切っておく
アプリの通知を切っておくだけで、スマホの使用時間を短くできます。
また、通知機能が、スマホ依存を悪化させるドーパミンを増加させるという学説もあるほどです。
アプリを整理して、通知を管理しましょう。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか?
スマホ認知症は、お年寄りから子どもまで発症する可能性があります。
最近では、文字の大きな高齢者向けのスマホが発売されるなど、高齢者の普及率も高まっています。
そのため、スマホに熱中してしまうことも少なくないです。
そのような場合には、周囲の人が声掛けを行い、使用時間を調整してあげましょう。