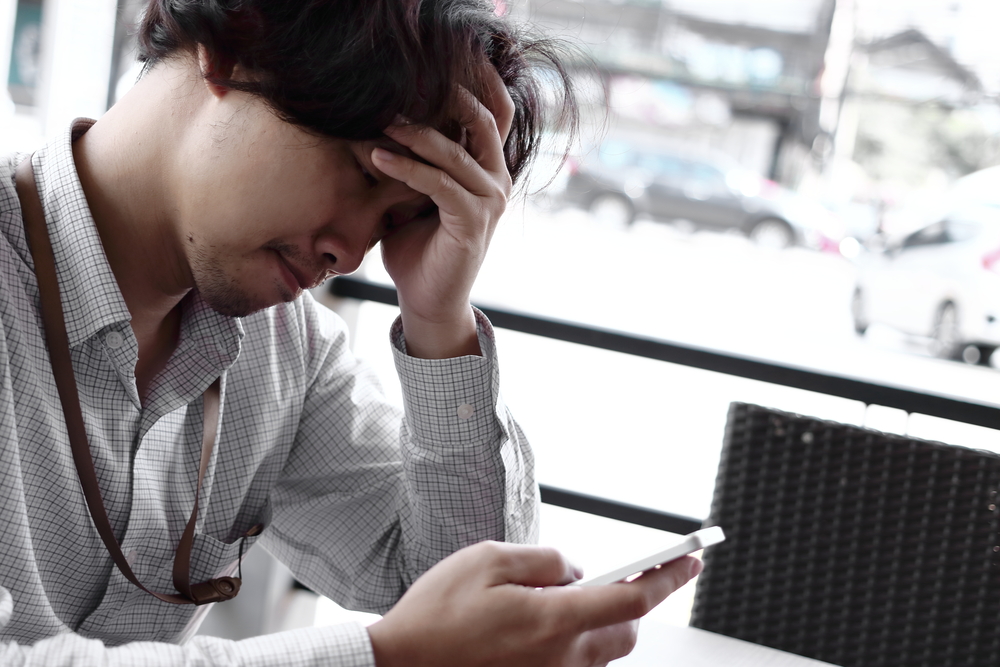寝たきりや認知症になると気を付けないといけないのが、床ずれです。
かかってしまうと皮膚に痛みやかゆみを感じてしまいます。
床ずれとは、布団や椅子と接触する皮膚部分に酸素や栄養が行き渡らなくなり細胞が死んでしまうことです。
実は、床ずれの対処を怠ると、最悪の場合命に関わることもあります。
今回の記事では、床ずれの原因や予防方法について解説します。
早速学んでいきましょう。
目次
1.床ずれとは


床ずれは、医学用語で「褥創(じょくそう)」と言います。
床ずれとは、布団や椅子と接触する皮膚部分に酸素や栄養が行き渡らなくなり細胞が死んでしまうことです。
皮膚が長時間、連続的に圧迫されて血流が悪くなることにより生じます。
症状としては、「赤み」や「かゆみ」、「痛み」、「ただれ」などが引き起こされます。
寝たきりで長時間同じ体勢でいると床ずれが発生する可能性が高いです。
2.起きやすい場所は?
床ずれが起きやすい場所は、肩甲骨や後頭部、腰など骨が出っ張っている部分です。
出っ張っている分、圧力がかかりやすく血流が悪くなりやすいです。
仰向けで寝ている場合は腰やかかと、横向きで寝ている場合は、足の付け根や肩などに起こりやすいと言われています。
床ずれが起こりやすい場所を把握することで予防がしやすくなるでしょう。
次の章では、床ずれが起こる原因について見ていきます。
3.床ずれが起こる原因


3-1.皮膚による原因
長時間同じ体勢でいると、圧迫や摩擦により皮膚が弱くなります。
また、高齢になると肌が乾燥しやすく、床ずれが起きやすくなります。
定期的に保湿クリームを塗るなど乾燥対策をしましょう。
3-2.身体的な原因
十分に食事を摂れていないとやせてしまい、より骨が出っ張りと床ずれになりやすくなります。
また、病気などで自由に体が動かせない場合、長時間同じ体勢から動けず床ずれに繋がってしまいます。
さらに、病状によっては痛みを感じにくくなるため、気づいたときには重症になっているという可能性もあります。
3-3.環境的な原因
介護の体制が整っておらず、体位変換が十分に行えていなかったり、不適切な寝具を使用していると床ずれの原因になります。
適切な介護体制と福祉用具をそろえましょう。
4.床ずれの予防法


4-1.体位変換を行う
定期的に体位を変換することが重要です。
姿勢を変えることで、同じ部位が長時間圧迫されることを防ぎます。
体位変換は2時間に1回を目安におこない、「仰向け⇒右向き⇒左向き」と体位を変えると効果的です。
体位を変えるときは必ず被介護者に声をかけてから行いましょう。
無理に体位を変えようとすると、被介護者だけではなく、介護者まで体を痛めてしまう危険があります。
4-2.スキンケア
床ずれの防止にはスキンケアが有効です。
高齢になると肌が乾燥しやすく、床ずれが起きやすくなります。
定期的に保湿クリームを塗るなど乾燥対策をしましょう。
また、おむつを着用している場合は、おむつの中が蒸れ皮膚が柔らかくなり床ずれを起こしやすくなります。
こまめにおむつの取り換えや蒸れのふき取りをすることで防止に繋がります。
4-3.皮膚摩擦やズレを防ぐ
シーツや寝間着のしわによって圧力が生まれ、床ずれを起こしやすくなります。
特に体位変換を行うときにしわがよりやすいです。
そのため、小さなしわでも皮膚摩擦を起こしてしまうため、きちんとしわを伸ばしましょう。
4-4.介護用ベッドを使用する
〇介護ベッド
体圧分散効果のある介護用ベッドは、肌が触れる面積をできる限り広くとって圧力を分散させます。
さらに、ベッドの高さや角度を変えることができ介護がしやすくなります。
介護ベッドを使えば、介護者の体にかかる負荷が小さくなります。
〇エアマットレス
エアマットレスとは、床ずれ防止のマットレスです。
マットレス内の空気が一定時間で膨らんだり縮んだりして身体にかかる圧力を分散させます。
〇体位変換器
体位変換器とは、被介護者の身体の下に器具を差し込んで、てこの原理を利用することで、身体を動かせるようにする器具です。
自力で寝返りができないと床ずれになる可能性が高まります。
しかし、体位変換器を使うと小さな力で体位変換が可能になり、床ずれの予防になります。
4-5.栄養管理
床ずれの予防には、圧迫を少なくすることだけではなく、皮膚や筋肉に十分な栄養を行きわたらせることが重要です。
健康な皮膚や筋肉づくりに必要な栄養素をしっかりとるため、バランスのよい食事を心掛けましょう。
水分摂取量にも注意し、体の内側から床ずれを予防しましょう。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか?
床ずれには、様々な原因があります。
原因を特定して有効な予防法を取りましょう。
症状が軽いからといって放っておいては、最悪の場合命にかかわる可能性もあります。
床ずれを発見した場合は、かかりつけ医に相談しましょう。